ベニスに死す
「アンチエイジングの専門家がナビゲート」(ガイド:塩谷信幸)
トーマス・マンの「ベニスに死す」。
ある高名な作家が避暑地の海辺で美少年を見かけ恋に陥る。やがてコレラがその避暑地に蔓延し始めるが、老作家は13,4才とおぼしい美少年に心をうばわれ、その地を離れようとしない。そして老いを嘆き、髪を染め、顔にメークを施し...といえば、ああ、トーマス・マンの「ベニスに死す」かとすぐおわかりになるでしょう。
これがヴィスコンティの手で映画化されたとき、賛否こもごもだったのを思い出します。
そもそも名作の映画化はハンディを伴います。
名作に傾倒すればするほど、読者の頭にはあるイメージが固定されていく。しかし、それは象徴というか抽象的な理想の姿で、現実には存在しない。どんなに見事に映像化しても、現実に現れるとぶち壊しになってしまう、という宿命を持っているようです。
原作の主人公はグスタフ・アッシェンバッハという作家ですが、映画では作曲家ということになっています。そもそもこれを書いているときは、マンはグスタフ・マーラーに熱中し、グスタフはそれからとったということですし、映画の中でマーラーの曲がまことに効果的に使われていることも評判になりました。
紆余曲折の後、アッシェンバッハはベニスに居座ることにします。
すると、「自分が惚れている甘美な少年にくらべて、自分の老いかけた肉体はいかにもいまいましく醜悪だった。白髪や、きつい顔つきをかがみで見ると、羞恥と絶望とに陥った。なんとか肉体的に若返って立ち直ろう」という気が起こって、ホテルの美容室に出かけるのです。
ここで老作家のアンティエイジングの旅が始まります。
「おつむりを元の自然の色に戻して差し上げましょう」という理髪師の屁理屈に乗せられ、髪を黒く染めます。さらに、「お顔のお肌を少々お直しすればよろしゅうございます」 とすすめられ、「瞼の下にちょっと手が加えられて目がいっそう輝きを増し、下のほうの、肌が薄茶色の皮のようだったところも薄く紅をさされてほんのりと赤みを帯び、血の気のなかった唇が苺色にふくれ上がり、頬や口の回りの皺、目の周囲の小皺にクリームを塗られ、若返らされて消えうせていくのを見た。―胸をどきつかせながら、彼は鏡の中に一人の若々しい男を発見」するのです。
上手いものですね、この描写。つい引き込まれて、僕でも試したくなりますよ??
このあたりをヴィスコンティは実にリアルに描きます。アッシェンバッハを演ずるのはダーク・ボガード、美少年タドチオは、ヨーロッパ中を捜してやっと見つけた子役だそうです。ちなみに美少年の母親はシルバーナ・マンガーノで、やはり貫禄でした。
やがてフィナーレがきます。
コレラに冒された老作家は、尚もタドチオの幻影を追いながら、砂浜のデッキチェアの上で、がっくりと息を引き取ります。
そのとき唇はゆがみ、「自然に戻した頭髪」から染料が黒々と流れ出し、ルージュの赤とコントラストを描きます。
ま、何もここまでやらなくても、というのが偽らざる感じでしたが、これはアンティエイジングへのレクイエムはたまたオマージュかなど下らぬ詮索をすれば、それこそトーマス・マンに「度し難い者、汝の名は美容外科医なり」と愛想つかされてしまうかもしれませんね。
(文中の引用は、高橋 義孝教授の名訳による。)
Written by 理事長 塩谷信幸
筆者の紹介

塩谷 信幸(しおや のぶゆき)
NPO法人アンチエイジングネットワーク理事長、北里大学名誉教授
東京大学医学部卒業。フルブライト留学生として渡米し、オルバニー大学で外科および形成外科の専門医資格を取得。帰国後、東京大学形成外科、横浜市立大学形成外科講師を経て、北里大学形成外科教授、同大学名誉教授。 現在、北里研究所病院美容医学センター、AACクリニック銀座において診療と研究に従事。日本形成外科学会名誉会員、日本美容外科学会名誉会員として形成外科、美容外科の発展の尽力するかたわら、NPO法人アンチエイジングネットワーク理事長、日本抗加齢医学会顧問としてアンチエイジングの啓蒙活動を行なっている。
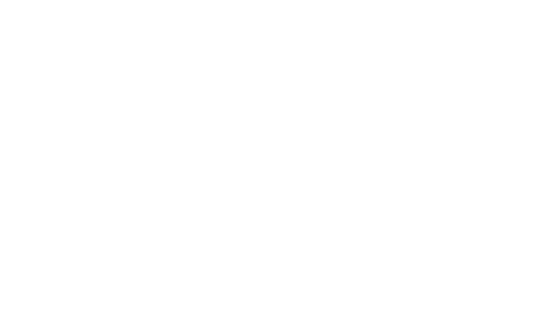
この記事が気に入ったら「いいね!」しよう
最新記事をお届けします










